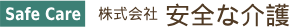- TOP>
- >
- 投稿者: anzen-kaigo
投稿者: anzen-kaigo 一覧
- 02/22
20252025.02.22- 面会の家族が食事介助を申し出たのでお願いしたら誤嚥事故発生、施設の責任は?
《検討事例》
頻繁に特養の入所者に面会に来る長男の妻が、いつものように食事介助を申し出たためお願いしました。ところが、介助中に利用者の顔が急にガクッと下を向いて動かなくなり、気付いた看護師が誤えんと判断し吸引を施行して救急搬送しましたが、病院で亡くなりました。病院に駆けつけて来た長男は、取り乱して泣いている妻を見て「入所者の介護は職員がやるべきではないのか?」と、施設の責任を追及します。施設長は、「介護したいとおっしゃればご家族の責任でお願いしています」と答えましたが、息子さんは納得していないようでした。施設長は相談員に「家族が介助中に起こした事故の責任は家族が負う」と一筆いれてもらおう」と言いました。《事例検討解説》
■家族の介助による事故で施設の責任が発生するか?
面会の家族が利用者を介助して事故が起きても、基本的には施設の責任は問われないでしょう。面会時に家族が利用者の介助を申し出ることは珍しくなく、施設は家族に介助上の注意を伝えてお願いしています。いくら「本来施設の職員がやるべき業務である」であっても、家族の介助の申し出をむげに断れませんから、施設は事故の責任を問われては困ります。
では、施設内の家族介助による事故で施設は責任を絶対に問われないか?というと、必ずしもそうではありません。介助業務を素人である家族に任せることに顕著な危険がある場合などは、事故が起こった時賠償責任が追及されトラブルになるかもしれません。本事例では次のような場合です。
1.入居者に摂食えん下障害があり家族にその認識が無い場合
入所前は摂食嚥下障害が無くその後機能障害や機能低下が生じていて、家族がこれを知らない場合には、きちんと誤えんのリスクを説明しておく必要があります。
2.介護職員でも食事介助が難しく、家族に任せることで明らかな危険が生ずる場合
匙への盛り方や口への運び方や姿勢など、介助方法が難しくこれを怠ると誤えんの危険があるような場合は、家族に任せると危険です。
3.誤えんのリスクが高く、しかも家族には誤えん発生時の適切な対処が期待できない場合
家族は介護のプロではありませんから、誤えん発生時の救命処置が正しくできるはずがありません。
また、取り乱す妻を気遣う息子さんの施設を咎めるような発言に対し、施設長が過敏に反応して責任回避の言葉を口にしてしまいましたが、事故直後の発言として適切ではありません。危うくトラブルになることころでした。利用者に事故が起こると、家族がその責任を追及してもいないのに過敏に反応して、すぐに施設側の責任回避ばかり主張する管理者がいます。事故発生直後のこのような管理者の責任回避の発言は、家族に対して「責任感が無い」「誠意が無い」という強烈な悪印象を与え、事故後の家族トラブルに発展するので注意しなければなりません。
■家族の介助に危険がある場合の対応
さて、このような面会の家族による利用者の介助に危険がある場合、どのように対応したら良いのでしょうか?利用者の家族が配偶者であれば、介助を任せると不安があるような、少しおぼつかないお年寄りもいますが、むげに断る訳にも行きません。
例えば「少し認知症がある夫が頻繁に訪ねて来て妻を歩かせる」「食べ物を持って来て居室で一緒に食べてしまう」などの場合、頭ごなしに「禁止」というのでは家族の気持ちに対する配慮に欠けます。完全看護の病院ではありませんから、介護職員も「余計なことをしないで下さい」とむげに断ることもできず困ってしまいます。
では、施設長が言うように、「家族が介助して事故が起きた時には“介助中の事故は家族が責任を持ちます”と一筆入れてもらう、という対応はどうでしょうか?これも適切ではありません。ご存知のように、“事故が起きても事業者の責任を追及しません”と一筆入れてもらっても法的な効力がありませんし、このような約定をさせることは消費者軽視になりますから控えなければなりません(※)。
少し考え方を変えてみたらどうでしょうか?施設サービスは利用者の生活を支えることですが、面会の家族も実は利用者の生活を支えています。面会の家族が利用者に寄り添って歩くことも、一緒に美味しいものを食べることも、単調な施設の入所生活の中では生活の彩であり、生活することの張りでもあり、利用者はみな元気になります。「家族と協力して利用者の生活を支える」という考え方をすれば、家族に適切な注意喚起を行った上で、安全に歩いてもらい、安全に美味しいものを食べてもらえば良いのです。
※消費者契約法によれば、「事業者を消費者との契約において、事業者の消費者に対する損害賠償責任の全部または一部を免除するような条項は無効とする(同法第8条)」とされています。
■高齢の家族への注意喚起の方法とは
事故防止の手法として、「利用者や家族の注意を喚起する」「注意を促す」という方法があります。利用者の自発行為で起こるような事故でも、施設職員は介護のプロですから、プロの立場からリスクを予測して本人や家族に必要な注意喚起をしておかなければなりません。
では、どのような方法で注意を喚起すれば、施設職員は介護のプロとしてやるべき安全配慮をしたことになるのでしょうか?面会の家族が配偶者のようなお年寄りであるケースも踏まえると、次のような注意喚起の方法が必要です。
①リスクを具体的に伝えて事故の重大性を認識させる
お年寄りはリスクに対する想像力や感受性が衰えてきますので、事故の結果どのような重大な事態になるのかを具体的に伝えなければなりません。「転倒すると危ないですから」ではなく、「転倒して入院すれば肺炎を起こして亡くなる人もいるのですから」と説明すれば良いでしょう。
②相手の理解力に即した平易な言葉で説明する
お年寄りは語彙が豊富ではありませんし、新しい言葉や難しい言葉は分からない人が多いですから、平易な言葉で分かり易く伝えなければなりません。介護の専門用語を使ってはいけません。「誤えんしたら大変ですよ」などの専門用語はできる限り避けて、「食べ物が喉に詰まったら窒息して死んでしまいますよ」と伝えれば良いでしょう。
③リスク回避の方法も具体的にアドバイスする
リスクを正しく認識できても、これを回避する方法が分からなければ、事故は防げません。ですから、分かり易くお年寄りにもできる事故の防止方法を伝えなければなりません。「注意して食べさせてください」ではなく、具体的にどのようにすれば良いかを伝えなければなりません。「4つくらいに切り分けてお茶と一緒に召し上がって下さい」と伝えれば良いでしょう。
- 02/22
20252025.02.22- デイの送迎時玄関で「ここでいいですよ」と奥様に言われ交替したら転倒
《検討事例》
Dさんはデイサービス利用している86歳の男性利用者です。通常移動は車椅子介助ですが、送迎時は居宅の門から玄関まで車椅子が使えず介助員が手引き歩行をしています。ある日、介助員がDさんの手を引いて玄関まで歩いたところで、奥様(82歳)が玄関のドアを開けて「ここでいいですよ」とDさんに手を差し伸べたため、介助員は「ではお願いします」と言って手を離しました。その直後にDさんがふらつき奥様が支えようとしましたが転倒、大腿骨を骨折してしまいました。デイサービスは「奥様にお引渡しした後なのでデイの責任はない」と主張しています。《事例検討解説》
■「ここでいい」と言われたら家族に任せて良いか?
原因分析に入る前に「奥様にお引渡しをしたのでデイの責任はない」という主張の是非について検討してみましょう。まず、デイサービスの送迎業務はどこで終了するのでしょうか?どこまでお送りすれば良いのでしょうか?「居宅の玄関まで送れば良い」と場所で理解している人も多いのですが、そうではありません。デイサービスの送迎業務の範囲は「居宅の玄関まで」などの場所ではなく、「居宅に帰着し安全な状態と認められるまで」です。なぜなら、送迎業務は単に利用者を輸送する業務ではなく、車両乗降や屋外歩行を介助して移動させるという施設の介護業務の一環とみなされるからです。
このような前提で考えると、介助員が奥様に利用者の歩行の介助を任せた時点では、送迎業務は終了していないことになります。そうすると、介助員が送迎業務中に家族から「こちらで介助しますのでいいですよ」と、介助を辞退されたことになります。では次の問題として、介助業務中に「家族自身で介助する」と介助を辞退されたら、家族に利用者の介助を任せても良いのでしょうか?答えはNoです。
■家族に任せる時は安全であることが条件
もちろん、たとえデイサービスや施設の業務であっても、家族がこれを代わりに介助することは、悪いことではありませんから、全てがいけないという訳ではありません。特別養護老人ホームなどでも、面会に来た家族が食事の介助をしています。しかし、本来施設職員が行うべき介助業務を家族に任せるのであれば、「家族で安全に介助できる場合」という条件が付くのです。
このように考えると、デイサービスの送迎の介助員は、本来車椅子介助の利用者を立位で手引き歩行している訳ですから、たとえ奥様が介助を申し出ても「ここでは危険ですからおうちの中で交替して下さい」と申し出を断って介助を続けなければならなかったのです。
■家族に介助を任せる時の注意事項を徹底する
本事例のように、家族が介助を申し出てこれをお願いする場面は送迎時だけではありません。デイサービスでも家族が来所されて、介助の手伝いをすることはありますし、入所施設の面会時にも同様の場面が考えられます。ですから、色々な場面における「家族に介護業務をお手伝いいただく要件」をある程度決めておいた方が良いと思われます。
デイサービスでは、家族が毎日居宅で利用者を介助していますから、家族が介助を申し出た場合、居宅での介助方法について家族と擦り合わせをする良い機会です。「デイサービスではこのように介助をしていますが、ご自宅で奥様はどのように介助をしていますか?」とお聞きして、介助方法についてプロとしてアドバイスができれば素晴らしいと思います。一方で、入所施設などでは、「家族が入所後の身体機能低下を理解していないため、昔の介助方法でやろうとしたらできなかった」というケースもありますから注意を要します。以上のように、本来施設がすべき介助を家族が申し出た場合については、介助をお願いする時の注意事項をまとめておいた方が良いでしょう。では、本人自身が介助を辞退して、「自分でやるから介助は必要ない」と申し出た場合はどうしたら良いでしょう?
■本人が介助を辞退したら自立動作に任せて良いか?
この場合も、家族が介助を申し出た時と考え方は同じです。つまり、本人自身が独りで安全にできると判断できる場合には、利用者の自身の自立した動作に任せて良い事になります。介護保険制度や福祉サービスの理念の大きな柱に「自立支援」という考え方があります。「本人自身でできることは本人にやっていただく」ということは介護職員の常識です。何でも気を回して本人ができることを介護職が手伝えば、過介護になって本人の自立を妨げますし、「人の手を借りずに自身でやりたい」という自尊心も奪ってしまうことになるからです。
ところが、このような介護の常識が裁判所には理解してもらえないらしく、介護職にとっては厳しい裁判の判決が出ていますので知っておいて下さい。次のような内容です。
デイサービスの利用者(要介護度2で杖歩行)が、デイサービス終了時にトイレに行きました。この時職員は介助を申し出ましたが、本人が「一人で大丈夫だから」と言って、トイレのドアを閉めてしまったので、トイレ内までは付き添いませんでした。ところが、被害者はトイレ内で転倒し大腿骨を骨折してしまったのです。被害者の家族は、たとえ本人が「一人で大丈夫だから」と言っても、歩行が不安定で転倒の可能性が高く介助すべきであり、デイサービスに過失があると訴訟を提起。裁判所は原告の訴えを認め賠償金の支払いを命じました。 (H17年3月20日横浜地裁判例)
事故の賠償訴訟の裁判では「危険があれば事故を回避する措置を講ずる義務がある」という考え方のみで過失を判断します。その考え方には、自立支援という介護業界では当たり前の観念が全く存在しません。「多少でも危険があると判断したら危険を回避するために介助しなさい」と決めつけるのです。自立支援も本人の自尊心への配慮も関係ないのです。
立場が違うと考え方も異なるので仕方ないのですが、裁判官にも少しは介護される人の気持ちも理解してもらいたいと思います。「危ないから」と言って自立した動作をさせてもらえず、全て制限されたり介助されたら、人は身体的機能が低下するだけでなく、生活意欲や精神の自立も失ってしまいます。前述の裁判官は将来自分が要介護になった時、「自分でできることは自分でやるから余計なことはす
- 02/22
20252025.02.22- 1年前にヒヤリハットが起きた保育園の裏口付近で今度は人身事故発生
《検討事例》
ある日の夕方、利用者送迎中のデイサービスの送迎車が、保育園の裏口の付近を通過しようとしました。保育園の裏口には、園児を迎えに来た母親が道路の脇で何人も立ち話をしていたので、運転手はこれを避けて通過しようとしました。その時、立ち話をしている母親の間から園児が飛び出してきて、徐行している送迎車の左前に衝突しました。すぐに119番通報し警察を呼びましたが、幸い軽症で済みました。翌朝のミーティングで、所長が他のドライバーに前日の事故について説明し注意を促すと、ドライバーの一人が「1年前に同じ場所で同じヒヤリハットがありました。今でもヒヤリハット報告書を持っています」と言いました。《事例検討解説》
■事故防止に活かさせないヒヤリハット
このデイサービスの所長は、日頃から事故防止活動に熱心に取り組み、「ヒヤリハットシートをもっとたくさん出すように」と職員を厳しく指導している人でした。その事故防止活動の管理者が、提出されたヒヤリハットシートの情報を読みもせずにバインダーに眠らせていたのですから、所長は立場がありませんでした。
“ヒヤリとした”“ハッとした”とう事故寸前の体験を記録し、この情報を職員が共有して事故防止に活かすことが、ヒヤリハット活動の目的です。ところが、このデイサービスではヒヤリハットシートを書いて提出することが活動の目的になっていて、ヒヤリハットシートが事故防止活動に全く活かされていませんでした。ヒヤリハット活動の本来の目的が忘れられていて形骸化しているのです。
特養などの施設でも同じことが言えます。特定の利用者などの転倒のヒヤリハット情報なども、シートに書いて提出するだけで、他の職員との情報共有さえできていないのです。せめて「ヒヤリハット情報は毎朝ミーティングで報告する」というルールにして、1年前のヒヤリハット情報を共有していたら、本事例の事故は防げたかもしれません。
■交通事故のヒヤリハット情報はどのように共有すべきか?
さて、送迎中の自動車事故のヒヤリハットはミーティングで報告するだけで、正確な情報が共有できるのでしょうか?転倒のヒヤリハットであれば「〇〇さんの歩行の介助中に膝折れして転倒しそうになった」という情報を職員が共有できれば、他の職員もその利用者の歩行介助時に膝折れによる転倒に備えることができます。
しかし、送迎中の自動車事故のヒヤリハットの場合、ヒヤリハット発生地点を正確に把握して、危険に対処する運転をしなければなりません。ヒヤリハット発生地点は、ヒヤリハットシートの文書を読んでも、また住所で示されても正確に把握することはできませんし、具体的なリスクの発生状況も文字では把握しきれません。では、ヒヤリハット地点と具体的なリスク発生状況を、どのような方法で共有したら、自動車事故防止に活かせるのでしょうか?
■ヒヤリハット発生地点は危険箇所マップで共有する
東京都のある社会福祉法人では、全てのデイサービスでヒヤリハットをビジュアル化する取組をしています。具体的には、危険箇所マップを作成してヒヤリハット発生地点を地図上で把握し、ドライブレコーダーの画像でリスクの発生状態をビジュアルに把握する活動をしているのです。
初めに危険箇所マップによる、危険箇所の把握と共有方法をご紹介します。送迎エリアを1枚の大きな地図にしてデイルームの隅に貼り出します。送迎中にヒヤリハットが発生すると、ドライバーはヒヤリハットシートを記入し提出した後に、マップ上のヒヤリハット発生地点に付箋を貼ってどのようなリスクが発生したのかを書き込みます。図のように、保育園のお迎えのママさんの影から園児が飛び出して来たら、「保育園送迎飛び出し注意」と記入します。もちろん、翌朝の朝礼でヒヤリハットを報告しますから、他のドライバーは発生地点を地図ですぐに確認できます。
デイサービスを訪れた利用者の娘さんがこのマップを見て、「私も注意しなくちゃ」と言って、スマホで写メして帰ったそうですから、家族にも事故防止の姿勢が伝わって評判は上々だそうです。
■ドライブレコーダーの画像を閲覧
次の事故発生状況の把握と共有方法です。ドライバーからヒヤリハットシートが提出されたら、所長はドライブレコーダーの画像をWEBで入手します。パソコンにヒヤリハット情報の画像をダウンロードしたら、始業点検前にドライバーを全員呼んでヒヤリハットの画像を見ながら注意を促します。ドライバーは臨場感溢れる画像で、自らがヒヤリハットを体験したと同じように感じるため細部にわたる安全配慮運転ができるようになります。図のような自転車の飛び出しの場面を見ていると、反射的にブレーキを踏もうとして思わず足が突っ張ってしまいます。
このようにして、ヒヤリハット発生地点と発生状況をビジュアルに把握することによって、その危険箇所地点に差し掛かった時に、自然に徐行運転ができるようになります。この社会福祉法人では定期的に全てのデイサービスの送迎車ドライバーを一堂に集めて、ヒヤリハット事例についてグループで討議する検討会も行っています。
- 02/22
20252025.02.22- 「他の利用者から30万円もサプリメントを買わされた」というデイのクレーム
《検討事例》
ある日、デイサービスの女性利用者Kさん(軽度認知症あり)の娘さんから次のようなクレームの電話が入りました。「母がデイサービスで仲良くなったMさんから、30万円分のサプリメントを買わされた。“デイの職員にも勧められた”と言っている。デイサービスで責任を取れ」というのです。デイサービスでは、職員がサプリメントの購入を勧めている事実はないし、Kさんは認知症が無いのだからご自分の判断で購入されたのでデイで責任は負えない」と答えました。すると、娘さんは「高齢者の詐欺被害が社会問題になっているのに、デイの配慮が足りない」として主張して市に苦情申立をしました。《事例検討解説》
■デイサービスに法的責任が無いことは明白だが・・・
デイサービスで知り合った利用者が、デイの外でもお友達付き合いをするようになりトラブルが発生しても、デイサービスには法的な責任もありませんし、トラブルを解決する義務もありません。その点で、本事例の所長が言っていることは、理屈では正しいことになります。しかし、本事例では良く話を聞いて相談に乗ったり、アドバイスをするなどして協力するくらいはできたはずです。そうすれば、少なくとも市への苦情申立は回避できたでしょう。
クレームの申立に対して「対応できない」と即答することは絶対に避けなければなりません。クレーム対応の手順では、「申し立ては一旦お預かりして対応方法を検討する」というのが基本中の基本なのです。申立内容をしっかり聞いて検討すれば、100%満足する対応ができなくても、お客様は対応の姿勢を評価してくれます。救いを求めて来ているお客様に目の前に門を閉ざすことは、強烈な悪感情につながるので要注意です。
■50万円分のサプリメントを売ることは特定商取引に該当する
さて、次に「他の利用者からサプリメントを大量に買わされた」というトラブルには、どのように対処したら良いのでしょうか?前述のようにデイサービス内で売買された訳ではありませんから、売った側のMさんに対して「デイの利用者には売ってはいけない」と禁止する訳にも行きません。
しかし、軽度の認知症の利用者が50万円もの大量のサプリメントを買わされたことは、販売行為として問題があります。この販売行為は特定商取引と言われ、「特定商取引法」という法律で厳しく規制されています。特定商取引とはいわゆる訪問販売のことですが、居宅に訪問して販売行為をする者の他、展示会やイベントに参加させたりして販売行為をする者も該当します。
特定商取引法は、販売者に対して勧誘を受ける意思の確認などを義務付けるほか、契約を締結しても8日以内であれば契約解除ができる(クーリングオフ)、通常の消費量を著しく超える購入契約(過量販売契約)は1年以内に契約を解除できるとして、取引の公正性と消費者被害の防止を図る法律なのです。
ですから、Kさんがサプリメントを購入して8日以内であれば、クーリングオフができるかもしれませんし、“通常消費する量を著しく超える量(加量販売契約)”とみなされれば、契約の解除ができるかもしれません。Mさんの販売行為を禁止することはできなくても、Kさんの娘さんに対して買ってしまったサプリメントの代金を取り戻す方法をアドバイスすることはできたはずなのです。
■特殊詐欺や悪徳商法から高齢者を守ることもデイの社会的責任
本事例のデイサービスの所長は、施設内の管理については意識が高いかもしれませんが、企業活動の社会的責任については認識が低いようです。近頃では、企業活動の社会的責任として、社会貢献活動が強く求められており、一般企業であっても地域の高齢者の安全に配慮する活動を行っています。特殊詐欺(オレオレ詐欺など)による高齢者の被害が社会問題になっていますから、銀行はATMに行員を配置して特殊詐欺の被害者を発見する取組を行っています。
デイサービスは、高齢者の生活を支えるという事業を営む介護事業者なのですから、特殊詐欺や特定商取引の被害から利用者を守る取組をもっと行うべきなのです。「施設内の事故やトラブルさえ防止すれば良い」と考えているのであれば、介護事業者としての社会的責任を放棄していることになります。
消費者庁が作成した「高齢者の消費者トラブル見守りガイドブック」では、「民生委員、ヘルパー、ケアマネジャーの方々は高齢者にとって心強い味方です」と言っています。在宅介護事業者はお年寄りの生活に密接に関わっているので、地域住民よりもお年寄りを守る責任は重いと言っているのです。施設内の管理だけにとらわれず、利用者の生活全般の安全に対しても配慮をすべきではないでしょうか?地域にしっかり根差した取組を勧めているデイサービスでは、職員が進んで特殊詐欺や特定商取引(法)を勉強して、独居の利用者などに絶えず注意を促しています。
■高齢者の詐欺被害防止にも取り組もう
では、デイサービスとして利用者の特殊詐欺や特定商取引の被害防止に対して、どのように取り組んだら良いのでしょうか?まず、職員が特殊詐欺や特定商取引について知識を持たなければなりません。職員を集めて相談員が勉強会を開くのもの良いですし、警察の生活安全課に防犯協会がありますから、ここにお願いすると講師に来てくれます。特殊詐欺はオレオレ詐欺や還付金詐欺などを、ニュースで報道していますから私たちも良く知っていますが、特定商取引についてはあまり知識が無いのでしょうか?高齢者に関わる代表的なものをご紹介しますので、ぜひ勉強して利用者に絶えず注意を促してください。
《特殊詐欺》
①オレオレ詐欺:電話で親族や会社の上司の名を語り、トラブルや交通事故の示談金名目で、現金を預金口座等に振り込ませるなどして騙し取る詐欺。
②還付金詐欺:税務署や市役所などかたり、税金や保険料、医療費の還付等に必要な手続きを装って、現金を預金口座等に振り込ませるなどして騙し取る詐欺。
③金融商品等取引名目の詐欺:実際には価値がない有価証券や架空の外国通貨などをあっせんし、現金を振り込ませてだまし取る詐欺。
《特定商取引※》
①訪問販売:自宅を訪問するなど、舗以外の場所で商品やサービスを不当な価格で売る取引。狭い店舗に人を集め巧みな話術で価値の低い商品を高額で売りつける(SF商法という)を含む。
②訪問購入:自宅を訪問するなどして「不要な貴金属を譲ってほしい」と持ち掛け、不当に安い値段で買い取る取引
③電話勧誘販売:電話で勧誘して不当に高額な物を大量に売りつける取引。
※特定取引は法律によって、クーリングオフや過量販売契約の解除権などが認められています。
- 02/22
20252025.02.22- 排泄の介助でトイレの外で待機中に便座から転落して重症、オムツでも仕方ないか?
《検討事例》
特養の職員Hさんは、左片麻痺で車椅子全介助の利用者をトイレに連れて行き、便座に移乗させました。利用者は、座位は安定しており本人の強い希望もあって、トイレ誘導で介助をしています。「終わったら呼んで下さい」と言ってドアを閉めて外で少しの間待ちました。1分もしないうちに、ゴンという鈍い音がしたのでドアを開けてみると、利用者が麻痺側の左前方に転落していました。利用者は床に頭部を強打して、意識不明となり救急搬送されました。Hさんは「座位が安定しない利用者はオムツでも仕方がない」と事故報告書に書きました。《事例検討解説》
■トイレ内に入れないので見守りでは転落が防げない
Hさんは転倒事故も転落事故も、職員の見守りによって防がなくてはいけないという考え方ですから、見守りができないトイレ内で便座から転落する危険があれば、「トイレでの排便は無理」という結論になってしまいます。Hさんは「座位が安定しない利用者はオムツでも仕方がない」と決めつけていますが、大切なことを忘れています。それは「便座から転落しないような対策」と「転落してもケガをさせない対策」を何もしてないで、自力での排泄は無理としていることです。まず、便座から転落する原因と、大きな事故につながる原因を考えてみましょう。
■便座から転落する原因
①便座がその人にとって高すぎる
多くの高齢者は体格が小柄で便座に座った時、両足の踵がしっかり床についていないため、座位が安定しません。80代の女性の下腿長(膝下の長さ)の平均は36センチで、普通の便座は床から42センチの高さですから、6センチも足りないことになります。
②移乗した時座位の安定を確認していない
便座への移乗を介助した時、介護職は座位の位置を確認しているでしょうか?便座は微妙なカーブを描いていて、正確に中心に座らないと座位が安定しません。移乗しただけで中心に座っているとは限りませんから、位置の確認が必要なのです。
③便座が大き過ぎる
体重が30キロ前半のような体格が小柄な女性では、お尻が小さすぎて便座の穴にすっぽりハマってしまう人もいて、便座の穴が大き過ぎてバランスを崩す人もいます。
④座位上の安定を支えるものがない
便座上で座位の安定を支えるものとして、壁の横手すりにつかまったり、可動式の手すりに捉まることが考えられます。しかし、手すりに捉まって座位を保持するには握力が必要ですので、握力の弱い人はかなり難しくなります。
■大きな事故につながる原因
①座位から直接頭部を床にぶつける
施設のトイレは健側にL字手すりがついていて、麻痺側がかなり広いスペースになっています。施設は車椅子が入るスペースがあるので麻痺側のスペースが広くなっていますから、この方向に転落すると頭部を直接床にぶつけて生命にかかわる大事故につながります。
②床が固すぎる
最近の入所施設ではトイレ内にもクッション性のある床材が使われおり、頭部を打った時の衝撃が吸収されるようになっています。しかし、多くの施設では床がタイルやクッション性がない硬い床材ですから、頭部を直接強打すれば生命にかかわる事故につながります。
■座位を安定させて転落を防ぐ対策
前述の便座から転落する原因と、大きな事故につながる原因を踏まえて対策を講じるとどうなるでしょうか?
①踏ん張れるように足台を作る
下腿長が便座に対して6センチも足りないのでは、両足の踵がしっかり床につきませんから、ほとんどの利用者に足台が必要になります。足を広げた状態でないと踏ん張れませんから、広めの足台を作ります。少し高めの足台を作り、少し膝が浮くくらいの物を作るのが良いでしょう。膝が少し浮く程度の方が臀部が少し沈んで、座位が安定するからです。
②移乗した時座位の安定を確認する
便座に移乗させてすぐにドアを閉めてしまう介護職がいますが、これでは安定した座位になっている確率は低いでしょう。まず、左右のズレがないか正面から確かめて、体幹が便座の中心に来ているかを確認して下さい。できれば、少し腰を浮かして「座りなおしてあげる」ほうが良いでしょう。本人に「座りやすいですか?」と確認することも忘れないで下さい。L字手すりの横手すりに手を置いてあげればより安定します。
③補助便座を使う
体重が29キロという特別小柄な女性利用者は、お尻も小さく臀部も痩せていたため、お尻がスッポリ便座の穴にハマってしまいました。ハマらないまでもこの状況に近い人は、座位が安定しません。幼児用に売っている補助便座を取り付けてあげれば、座位は確実に安定します。入所施設でこの補助便座を使っている施設はあまり見たことがありませんが。
④座位の安定を支える道具
最近では、L字手すりや可動式の手すりの他に、両側に稼働式の肘掛(肘置き)がついているものが多くなりました。握力のない利用者でも腕を両側に載せることができますから、座位が安定すると同時に、左右にバランスを崩しても便座からの転落も防いでくれます。
また、数年前に座位の安定を支える画期的な道具として登場したのが、「前手すり」です。便座に移乗した後、壁から利用者の前に降りて来て、両腕を載せることができます。この「前手すり」は最近の入所施設では、「標準装備」と思えるくらいたくさん付いていて大変安心です。両側の肘置きと前手すりに囲まれていると、バランスを崩して転落しそうになっても、まず落ちることはあり得ませんから転落防止の切り札と言えます。
■転落しても大ケガをさせない対策
さて、最後に便座から転落しても大ケガをさせない対策を考えます。本事例のように、左片麻痺の利用者が麻痺側前方に転落すると、床に頭を直接打ち付けるために生命にかかわる事故となります。もちろん、床材をクッション性の高いものに替えたり、前手すりなどを設置できればこのような事故が起こることはありません。しかし、かなりの費用がかかりますから、気軽に設置すると言う訳には行きません。
本事例の施設では、フロアごとに2つだけトイレを改修して肘置きと前手すりを付けました。便座からの転落の危険のある人だけ、このトイレを使うことに決めたのです。また、ある施設ではL字手すりを使えない重度に利用者に対しては、逆向きのトイレの使い方に変えました。つまり、左麻痺の利用者は左側にL字手すりがあるトイレを使うのです。こうすれば、麻痺側に転落した時、壁に寄りかかるので床に頭を直撃しないで済みます。自力で手すりにつかまれない利用者であれば、手すりの位置はどちらでも同じですか
- 02/22
20252025.02.22- 「1日5回口腔ケアをすべき」という家族の要求を断ったらトラブルに
《検討事例》
ある特別養護老人ホームに入所した91歳の女性利用者の娘さんが、1日5回口腔ケアをして欲しいと言ってきました。「以前肺炎で入院した時に、口腔ケアを徹底するように医師から言われた」というのです。「1日3回で十分口腔内は清潔にできます」と言うと、娘さんは「施設サービス計画書に書いてあるのだからやるべきだ」と言います。計画書を確認すると「誤えん性肺炎防止のために口腔ケアを徹底する」と書いてあります。相談員は「計画書は援助目標を書いてあるので、口腔ケアの回数を言っているのではありません」と理解を求めましたが、娘さんは納得してくれません。口腔ケアは1日何回やるべきでしょうか?《事例検討解説》
■施設サービス計画書は契約書である
施設サービス計画書は相談員が言うように、ケアプランのように援助目標を記載するものなのでしょうか?実は施設サービス計画書は、契約書と同等の法的拘束力がありますから、計画書に記載してしまったら、契約条項と同じ意味を持ちます。ですから、施設サービス計画書に記載したことを実行しなければ債務不履行、つまり契約違反となります。
施設と利用者との間で締結される契約内容は、入所契約書のみで決まる訳ではありません。通常入所契約を取り交わす時には、入所契約書と重要事項説明書に印鑑を押しますから、この2つの書類が契約書であると思われていますが、そうではありません。
入所契約書や重要事故説明書には全ての契約者に共通する一般的条項しか記載されていません。施設の個別の利用者にどのようなケアを具体的に提供するのかは、施設サービス計画書に記載されて初めて明らかになるので、計画書も契約書の一つなのです。ですから本事例のように、 「誤えん性肺炎防止のために口腔ケアを徹底する」と記載した場合、他の利用者と同じ回数では徹底したことにならず、少なくとも1日4回以上の口腔ケアを約束したとみなされます。
■「歩行は常時見守り必要」と計画書に記載したが
本事例のように、口腔ケアの回数であれば家族に説明して理解を求めることもできますが、もっと重要な事項を間違って記載して大きな問題になった事例があります。あるデイサービスで、認知症の利用者が椅子から急に立ち上がって、そのまま転倒して骨折してしまいました。デイサービスでは、「急に立ち上がって転倒した場合、職員は対応しきれない」と理解を求めましたが、家族は「通所介護計画書に“歩行は常時見守りが必要”と書いてある。見守ってくれなかったから転倒した」とデイの責任を追及してきました。
通常防ぎきれない事故であれば、過失にはなりませんから賠償責任は発生しません。しかし、通所介護計画書に「常時見守り」と書いてしまったら、見守らずに転倒させれば契約違反になり、債務不履行として賠償責任が発生します。利用者を常時見守ることは不可能ですから、できないことは計画書に書いてはいけません。
■契約書であるという認識で作成を
以上のように、施設サービス計画書などの介護計画書は、個別利用者に具体的にどのようなサービスを提供するのかを記載する重要な契約書なのです。しかし、計画書の内容をチェックしてみると、本事例のように「徹底する」「努力する」などの曖昧な表現が多く、いざという時トラブルになりかねません。施設のケアマネジャーは、介護計画書が契約書であるという認識で、できる限り正確な表現で記載する必要があります。
ある施設のケアマネジャーが、本人が希望しているからと言って「年内に墓参りに連れて行く」と計画書に記載して問題になりました。何の相談も受けていない介護主任は「ほとんど寝たきりで外出には危険が伴うので絶対に無理だ」と主張します。家族が「ご厚意はありがたいのですが、うちのお墓は高い階段の上にあるのでとてもたどり着けませんよ」と言ってくれたので、幸いトラブルにはなりませんでした。
居宅介護支援事業所のケアマネジャーが作成するケアプランであれば、「援助目標」の欄に“墓参り”と書いて、実現に努力する旨を記載しても良いのですが、施設サービス計画書は、提供するサービスを記載する契約書ですから、慎重に作成しなければなりません。
- 02/22
20252025.02.22- 前夜転倒し経過観察中に利用者を何も知らないPTがリハビリを施行
《検討事例》
認知症があり自力で歩行できる老健の利用者Kさんが、夜間居室で転倒しました。手当てをした看護師は骨折の可能性があるが、痛みがひどくないので翌朝の受診としました。ところが、翌朝受診同行のために家族が来所し、居室に行ってみるとKさんが居ません。居室担当の介護職員に尋ねると、「PTが来てリハに連れて行った」と言われ、「転倒した母にリハビリをするとはどういうことだ?」と家族が激怒しました。受診するとKさんは大腿骨を骨折しており、老健では「介護職員が申し送りを聞き逃したことが原因」と謝罪しました。《事例検討解説》
■申し送りを聞き逃した職員のミスだろうか?
老健側はKさんの転倒事故の報告を聞き逃した居室担当の介護職員のミスとして謝罪しましたが、PTも少し注意が足りませんでした。PTは機能訓練を行う前に、利用者の心身の状況を正確に把握し、機能訓練に適した状態であるかを的確に判断しなければなりません。体調がすぐれない、関節などの痛みがある、認知症の利用者で精神状態が安定していないなど、リハビリ(機能訓練)に支障があるような状態であれば、施行を中止しなければならないからです。
しかし、認知症の利用者本人から生活状態や前日の出来事を詳細に聞き出すことは難しく、毎回機能訓練のたびにチェックを徹底することは困難です。ですから、Mさんを機能訓練に連れ出す前に、Mさんの心身の状況などについて情報が確認できるような仕組みを作っておかなければならないのです。居室担当やPTのミスとして問題を片づけてはいけません。
前日の晩に転倒して応急処置をして経過観察中というのは、「ひょっとしたら骨折しているかもしれないし、頭部を打撲しているかもしれない」という、容態が不明確で不安な状況にありますから、Mさんに関わる全ての職員が転倒事故の情報を共有して絶えず気に掛けるべきなのです。介護職員でも転倒の情報を知らなければ、いつもと同じ方法で排泄の介助をしてしまうかもしれません。
Kさんのベッドの床頭台の近くの壁に「○月○日夜転倒あり、経過観察中です」と転倒の情報を貼っておくだけでも、PTはKさんを機能訓練に連れ出すことは避けられたはずですし、他の職員が関わる時にもその安全に配慮ができます。
■事故直後に全職員が情報を共有する仕組がない
前述のように、「転倒したが経過観察中」という状態は、正確な容態は不明で受診方針も未決定な宙ぶらりんの状態で、対応が難しい状況にありますから、骨折などの最悪のケースを想定して、職員は慎重に対応しなければなりません。
そのためには、本事例のように口頭での報告・連絡を徹底して、全ての職員が情報共有を図ることも大切ですが、以前と異なり職員の勤務シフトが複雑になり、職員が集合して申し送りということが難しくなってきました。日勤、夜勤の他に早出・遅出など出勤時間が異なる職員が増えているのです。すると、口頭では徹底することが難しくなりますから、事故報告書やヒヤリハットシートなどの帳票を使って全ての職員に知らせる必要が出てきます。
しかし、事故報告書もヒヤリハット報告書も事故直後に起票される訳ではありませんから、翌朝経過観察中の時点では提出されていない施設がほとんどでしょう。ですから、Kさんが前夜転倒して経過観察中という情報を全ての職員が共有するということは、どの施設でも難しくなっているのです。では、事故直後に全ての職員がKさんの前夜の転倒の事実と経過観察中であるという状況を、情報共有するためにはどのような仕組を作ったら良いのでしょうか?
■経過観察中の利用者の情報共有の方法は?
本事例の施設では、Kさんの家族からのクレームを重く見て、経過観察中であっても転倒などの事故の事実を職員全員が情報共有する仕組を作ることになりました。まず、転倒などの事故が発生して経過観察する場合には、経過観察と判断した直後に「事故速報」という簡単な帳票を作って、ナースステーションの掲示板と、居室の壁に貼り出すことにしました。
この「事故速報」を初めは手書きで書いてコピーし貼り出していましたが、後日事故報告を定型フォーマットに入力することになり、パソコンで入力して速報用の出力用紙を打ち出すようになりました。同じ入力フォームから「事故速報」「市報告用」「法人報告用」「再発防止策記入用」など、様々な出力フォームを作って同じことを何度も書かなくて済むようにしたのです。
このように考えると、従来からの事故報告書は事故が発生すると翌日くらいには起票し、同時に事故原因や再発防止策が記入するのが習慣になっていました。しかし、迅速に事故事実を共有するための速報は発生直後に必要になる一方で、原因分析や再発防止策を記入する用紙は、現場でカンファレンスを行いじっくり時間をかけて検討しなくはなりません。つまり、事故報告書は速報機能や、現場でカンファレンスをして報告する機能など、多様な機能が必要なことになります。1枚の用紙で「事故が起きたらすぐに出しなさい!」では、原因分析も再発防止策も十分に検討できないのです。
■ショートの事故がデイに伝わっていない
本事例の施設では、事故速報を出すようになってからは、現場の職員が事故情報を迅速に共有できるようになりました。ところが、次のようなトラブルが起きて再び見直しの必要に迫られました。
Mさんは施設のショートステイを利用中に転倒して、手首をねん挫してしまいました。そして、以前から利用していた同じ施設の併設デイサービスを、ショート退所後に再び利用しました。ところが、デイの職員が「Mさんがレクリエーションに参加してくれないと盛り上がらないから」と執拗に誘って、レクリエーションに参加させてしまったのです。家族は「転倒してケガをしているのに、デイでレクリエーションをさせるとはどういうことか?」とクレームになりました。
ショートステイと併設のデイサービスを利用している利用者から見れば、「同じ施設なのだから転倒したことはデイにも連絡されているはず」と考えるのです。ところが、ショートで起こった事故などの情報は、併設デイサービスには伝わっていませんから「同じ施設なのに配慮が足りない」というクレームになるのです。今度は併設の施設との事故情報の共有の方法を考えなければなりません。
- 02/22
20252025.02.22- デイの送迎車が追突され興奮した利用者が脳梗塞発作、施設の責任が問われる?
《検討事例》
真夏のある朝、デイの送迎車が一人目の利用者Yさんを乗せた直後に、他車に追突されました。バンパーに傷もつかない程度の衝突で、Yさんの身体にも影響は無く救急車を断りました。ドライバーはすぐにデイに連絡を入れ、他の利用者のお迎えの手配をして、現場検証の間Yさんと30分くらい車内で過ごしました。ところが、デイに到着するとYさんに意識低下が起こり、病院に救急搬送しましたが、高血圧症の悪化による脳梗塞発作と診断され、介護度が悪化してしまいました。Yさんは血栓予防薬と血圧降下剤(利尿剤)を服用していたので、追突事故での興奮と脱水が原因とされました。デイサービスでは、追突事故の加害者が補償するものと考えていましたが、加害者の自動車保険から支払われずデイの責任だとして家族から賠償請求されました。《事例検討解説》
■なぜ追突事故の加害者から補償されないのか?
追突事故が起こらなければYさんは脳梗塞にはなりませんでしたから、一見Yさんの脳梗塞発作は追突事故の被害のように思えます。しかし、Yさんは事故発生時に身体に何のショックも受けていません。つまり、この追突事故とYさんの脳梗塞には、「直接的な因果関係が無い」ことになります。事故で骨折し入院した後に肺炎で亡くなっても、事故と肺炎には因果関係が無いため、通常加害者が加入している自動車保険から死亡保険金は支払われないのです。
また、追突事故の加害者は被害者に対して救急車の要請を申し出ており、警察の届け出も行っていますから、事故発生時に被害者に対して行うべき道路交通法上の義務(事故発生時の救護措置)を全て果たしています。すると、加害者側(損害保険会社)の“事故と脳梗塞には因果関係が無い”という主張は正しいことになり、Yさんの脳梗塞の責任を追突事故の加害者(保険会社)に負わせることはできないのです。では、Yさんの家族が主張するように、Yさんの脳梗塞による損害に対してデイサービスの責任はあるのでしょうか?
ご存知のように、デイサービスの業務中に発生した事故で利用者に損害が発生し、デイサービス側に過失があれば安全配慮義務違反として、損害賠償責任が発生します。この追突事故発生時のデイサービスのYさんへの対応に過失があるかどうか検証してみましょう。
■デイサービスの安全配慮義務は広範である
デイサービスでは入所施設ほど厳密ではありませんが、既往症や疾患などの健康状態の情報を把握し、レクリエーションや入浴前には、基本的な健康チェックを行っています。このように、デイサービスでは入施設ほどではありませんが、介護事業者としての健康管理に関する基本的な安全配慮義務を負っています。
ではYさんの場合、デイサービスに求められる健康上の安全配慮義務はどのようなものでしょう?Yさんは脳梗塞の既往症がありますから、脱水や低カルシウム血症などには注意しなければなりません。また、高血圧症ですから血圧上昇につながる高温の環境などには注意が必要ですし、血圧降下剤として利尿剤も飲んでいることから脱水は要注意です。
ところが、Yさんは事故発生時後送迎車内で30分間待たされてしまいました。Yさんは高血圧症で多発性脳梗塞の既往症がありますから、事故現場の車内に長時間留め置かれて、車内から出たり入ったりすれば血圧上昇と脱水が起こるかもしれません。珍しい体験に興奮すれば血圧に拍車がかかります。
このようなYさんの健康状態に配慮すれば、Yさんを居宅にいったん戻して涼しい場所で落ち着いてもらったり、デイのスタッフを呼んでデイにお送りすることもできたはずです。もし、事故後に現場に長時間留め置かれたことがYさんの脳梗塞発症の原因だとすれば、デイサービスの過失は否定できないかもしれません。
■送迎中のアクシデント全てに適切な対処できるか?
さて、本事例の場合運転手の対応に問題があるとしても、そもそもこのような状況で運転手に全ての判断を委ねて良いのでしょうか?送迎車の運行中には様々なアクシデントが起こります。高齢者ですから、運行中に利用者が体調急変を起こすかもしれませんし、持病が悪化するかもしれません。
最近では外注や嘱託の運転手など介護の知識の乏しい運転手が多くなっていますから、利用者の疾患など基本的な利用者の情報を知らない運転手に対して、アクシデント発生時に適切な対処を期待することに無理があるのです。「送迎中に予期せぬアクシデントが発生した時は、デイに連絡を入れスタッフの指示に従う」として、デイのスタッフの指示に任せているところもありますが、デイのスタッフも適切な対応ができる保証はありません。
運行中に最後列のシートの利用者の姿が見えなくなり、施設に到着した時はシートに横たわっていた、という事例があります。運行中の想定されるアクシデントが明確になっていませんから、運転手はアクシデントの発生に気付かないのです。このように、「送迎時のアクシデントへ対応方法」が場当たり的で、基本的なルールが無いのですから、適切な対応を望むべくもありません。
■アクシデント発生時の対応のルール化
送迎時に発生するアクシデントを具体的に想定して、「どのようなアクシデントにどう対応すべきか?」を決めておかなくはなりません。次のようにアクシデントを想定して、対処方法を決めておくと良いでしょう。
①運行中に発生した利用者の異変(急変)②車内での利用者の事故(転倒やシートからの転落)③居宅と送迎車間の移動中の事故④自動車事故による利用者のケガや遅延⑤その他の交通状況などから発生するアクシデント
この5項目に分けて、具体事例を挙げて運転手が何をすべきか、デイサービス側ではどのようにフォローするのかを具体的に決めます。例えば、「送迎車運行中に利用者が意識混濁を起こした」とアクシデントが発生した場面を想定してみましょう。
【運転手自身の対応】「その場でハザードランプを付け路上の安全な場所に停車する。」「利用者は動かさず安静状態を保つ」「場所が分かれば携帯で救急車を要請、分からなければ近所で住所を聞いて119番する」「デイのスタッフが到着するまで利用者の経過を報告する」
【デイのスタッフの対応】「家族連絡を入れ状況を説明して了解を得る」「本人対応のため相談員などスタッフが現場に急行する」「搬送先が判れば家族に連絡する」「他の利用者の迎えに行く車両を手配する」
このように様々なアクシデントを想定して、運転手とデイのスタッフの対応をルール化しておけば、いざと言う時にも適切な対応ができるのです。
- 02/22
20252025.02.22- 介護職員が利用者の写真を顔加工して人格を貶めた、家族が市に虐待通報
《検討事例》
ある特養の職員通用口の外の喫煙所で、二人の若手男性職員がスマホを見せ合って大きな声で笑っています。「この顔のいじり方最高におもしろ!ラインで送れ」「みんなにも送ってやれよ、受けるぜ」と。どうやら今流行りの顔加工アプリで遊んでいるようです。そこへ運悪くある利用者の息子さんが、駐車場へ行くための通路を歩いて来ました。息子さんに気付いた職員がすぐにスマホを隠して、もう一人に「おい、しまえ」と言って息子さんに会釈しました。
息子さんは「今何を隠したんだ?」と笑いながら、背を向けていた職員のスマホをのぞき込みました。画像を見た息子さんは血相を変えて「それ、うちの母親だろう!」と職員の腕をつかみました。職員は「違いますよ、〇〇さんじゃありませんよ」と言いましたが、そこには顔が加工され首から下を入れ替えられた、他の女性利用者の写真が写っていました。
息子さんが職員からスマホを取り上げ、施設長に抗議すると、施設長は「悪ふざけでも少し行き過ぎていますから、二人にはよく言って聞かせます」と答えました。息子さんは激怒して「介護職員がこんなことをしていいのか?これは虐待だろ!」と主張し、取り上げた職員のスマホを撮影してそのまま市役所に行って介護保険課に提出しました。
市の介護保険課では、「虐待認定はできないが介護職員として不適切な行為であり、コンプライアンスを徹底するよう指導する」と回答しましたが、息子さんは納得しません。今度は家族会で問題にして、「施設は不適切なケアが蔓延している。職員を懲戒処分すべきだ」と主張します。施設では「法律や就業規則に違反した訳では無いので、懲戒処分にはできない、コンプライアンス管理を徹底する」と回答しましたが、息子さんの追及はなかなか収まりません。《事例検討解説》
■コンプライアンス違反の行為とは何か?
市は「コンプライアンスを徹底するように指導した」と言い、施設は「コンプライアンス管理を徹底する」と言います。最近このような明確に違法性が指摘できないようなケースで、頻繁にコンプライアンスという言葉が使われます。コンプライアンスとはどういう意味で、この施設は何をどう徹底するのでしょうか?
「コンプライアンス」という言葉は通常「法令順守」と訳されますが、法令を守ることだけではありません。もっと広い意味で「法令順守も含め企業が自主的に企業倫理に沿った企業運営をすること」を意味します。
ですから企業は社員が企業倫理に反する行為をしないように体制を作り、社員には企業倫理に沿った行動を守らせなければなりません。ここで企業倫理とは企業に都合の良いものではなく、社会倫理に沿ったものであることは言うまでもありません。ですから、社員は法律に違反しなくても企業倫理や社会倫理から外れる行動をすれば、コンプライアンス違反となるのです。
整理すると次のようになります。
①法律(法令)に違反する行為 (刑法や条例に違反し罰則が科させる)
②他人の権利を侵害する行為(不法行為として賠償責任が発生する)
③お客様との契約に違反する行為(債務不履行として賠償責任が発生する)
④就業規則など業務上の規律に違反する行為(懲戒処分の対象となる)
⑤社会倫理に反する行為(社会のモラルから外れる行為)
⑥介護の職業倫理に反する行為(不適切なケア・介護職員として不適切な行為)
ところで、本事例の職員の利用者の顔加工行為はどのコンプライアンス違反に当たるのでしょうか?施設側では、「介護職員として不適切な行為」として④の行為として捉えているので、懲戒処分を行き過ぎと考えているようですが、これは間違いです。
人の容姿を本人の了解なく撮影する行為は、肖像権の侵害という人権侵害行為であり、不法行為となりますから、②に該当することになります。顔の加工方法が本人に侮辱的なやり方であり、多数の人の目に触れれば刑法の侮辱罪で①該当する恐れもあります。
コンプライアンス違反のクレームは、過度な正義感に基づくクレーマーのように考える傾向がありますが、事業者はもっと慎重に違法性などをチェックしなければなりません。本事例で施設は、顔加工の方法が侮辱的かどうかを判断して、加工された画像がどこまで拡散したかを確認の上、本人と家族に報告して謝罪すべきだったのです。
■コンプライアンス研修
さて、市から指導された「コンプライアンス管理の徹底」とは、具体的に何をしたら良いのでしょうか?「職員にコンプライアンスを守らせろ」と管理者に指導しても、コンプライアンスが何かをきちんと整理できている管理者は少ないですから、前述の4種類のコンプライアンス違反行為を管理者に徹底しなければなりません。管理者研修では事業者や職員個人に対する法的責任などについて教え、管理の徹底手法についてポイントを講義します。
〇コンプライアンス管理の手法
・守るべきルールを事例を交えて具体的に教える
・ルール違反に対する罰則を具体的に教える
・ルール違反に至った原因を分析しルール違反をなくす
管理者研修の次に、職員には具体的な違反事例を示して研修を行う必要があります。私たちは次のような介護事業で重要なコンプライアンス違反の行為について、具体的な事例を挙げて職員研修を行い「やってはいけない行為」を説明しています。
〇職員研修で教えるコンプライアンス違反行為
1.虐待行為
高齢者虐待防止法で定義される虐待行為のほとんどが、刑法の犯罪に該当しますから「虐待行為は犯罪」と認識しなければなりません。
2.身体拘束
不当な身体拘束は介護保険法に違反するだけでなく、悪質な場合刑法の逮捕監禁罪になることもあります。
3.ルール違反などの悪質な事故
介護マニュアルの安全ルールに違反して、故意に危険な介助を行い重大事故を起こせば、業務上過失致死傷罪として裁かれることもあります。
4.契約違反
個人情報の漏洩などお客様との契約に反する行為で損害が生じれば、その損害を施設が賠償しなければなりません。
5.就業規則や服務規律違反
お客様に損害が発生しない行為でも、職員として業務上守らなければならない就業規則や服務規律に違反すれば、懲戒処分の対象となります。
6.不適切なケア、不適切な言動
明確な虐待や身体拘束に至らない行為でも不適切なケアを行ってはいけませんし、介護職員として相応しくない不適切な言動も慎まなければなりません。介護職員には労働契約上の職務専念義務や企業秩序遵守義務があり、懲戒処分になることもあります。
少し前から、保育従事者のコンプライアンスが問題にされ、「不適切な保育」と言う新しい言葉を耳にするようになりました。0歳児の足を持って逆さに吊るす行為は明らかな違法行為ですが、幼児に下着のまま食事をさせることも「不適切な保育」とされて糾弾されました。
当初は企業行動の法令順守が目的とされた“コンプライアンス”はその意味が拡大し、一般市民が要求する多様な規範基準が企業に突き付けられるようになっています。SNSによる私的正義感による企業行動の糾弾も、コンプライアンスの拡大を助長しています。このコンプライアンスの膨張拡大の影響を経営者や管理者はきちんと理解し、市民的倫理規範に合わせていかなければなりません。
先日デイの外出行事で利用者の持っていた障害者手帳で障害者割引を使ったら「制度の趣旨を逸脱している」と家族から抗議がありました。法律にも規則にも違反していませんが、介護福祉従事者という一段高い職業モラルを基準に考えれば、家族の指摘はもっともなのです。
- 02/22
20252025.02.22- グループホームの外出行事中に行方不明になった利用者が3日後に警察に保護
《検討事例》
グループホームの外出行事で、有名な神社に花見に行きました。出発した時は曇りでしたが、到着すると小雨が降って来て、傘をさして参拝することになりました。職員3名と利用者5名(うち1名は車椅子)で参拝し、送迎車に戻ろうとすると、Mさんが見当たりません。まだ、午後2時だったので、神社を職員でくまなく探しましたが、5時になっても見つからず家族連絡の上警察に捜索願を出しました。デイの職員総出で探しましたが、その日は発見に至らず、3日後になって隣の市で警察に保護され、家族と大きなトラブルになりました。施設長は、「原因は職員配置が不足していたこと」と、家族に謝罪しました。《事例検討解説》
■職員配置は事故原因ではない
この事故で、家族と大きなトラブルになったグループホームでは、重大な問題と受け止め原因と対策を話し合いました。すると、「職員配置に問題があった」という意見が大半を締めました。つまり、5名の利用者(1名は車椅子)に対して職員3名では少ないので、人数を増やすべきだったというのです。本当にそうでしょうか?では職員を何名に増やしたら事故は防げたのでしょうか?
介護職員は自分たちの見守りによって、全ての事故を防ごうとするので、事故が起きると職員数が足りなかったなどと、的外れな指摘をしてしまいます。この事故では、職員配置の問題より「なぜ小雨の中人が混んでいる神社に行かなければならなかった」という方が問題なのです。外出行事は施設内とは環境が異なり、天候などの外的な条件に著しく左右されますから、本事例の事故原因の第一は、「わざわざ小雨の中人混みに出かけたこと」だったのです。
職員は外出行事先の選定の問題になると、「この地域だったら○○神社が有名だから」と、名所のような場所を選びますが、利用者はそんなことにこだわるでしょうか?何十年も地域で暮らしていれば、名所など何度も訪れていて今更行こうと思わないでしょう。外出行事はみんなででかける非日常が楽しみなのですから、場所はどこでも良いのです。■なぜ職員だけで捜索するのか?
次の原因は、職員だけで3時間も探していたことです。人出の多い混雑した神社で、職員2名(1名は他の利用者の対応)で認知症の利用者を探し出せる訳がありません。たとえ、天候などの外的な条件が悪くなくても、職員が利用者を見失うというミスは起こり得るのですから、もっと有効な対応方法を決めておかなければなりません。具体的には、神社の管理事務所などの係員に応援を求めたり、放送を使って呼び出しをすると決めておけば良いのです。結果的に、すぐに発見できなかったことで、神社の外へ出て隣の市まで歩いて行ってしまい、翌日夜まで発見できず大きな騒ぎになってしまったのです。行方不明の対策は見失わないことも大切ですが、見失った時どのように効果的な捜索ができるかにかかっていると言っても過言ではありません。
また、見失ってすぐに家族連絡を入れなかったことで、家族トラブルが大きくなりました。こんな時家族は「すぐに発見できたら行方不明は起きなかったことにするつもりだったのだろう」と隠ぺいの意図を疑い、著しく信頼感を損ないます。■あらかじめ予想されるトラブルへの対処方法を決めておく
グループホーム内だけでは、単調な生活になってしまいますから、散歩に行ったり外出行事を行いのはとても良い事ですが、施設内と違い屋外は天候などの外的条件に左右されますから、場所とタイミングを選ばなければなりません。まず、大雨など極端な悪天候であれば行事を中止にできますが、今回のように微妙なケースは判断に困ります。このようなケースに対応するには、あらかじめ屋内の外出先を決めておき、前日に変更することで対応できます。利用者はみんな楽しみにしていますから、「目的地に着いてみたら小雨が降って来た」というケースでは、ほとんど中止できず決行してしまうからです。
さて次の問題は、外的条件が悪くなくても利用者を見失うというミスは起こり得るのですから、見失った時の対応方法をあらかじめ決めておかなければなりませんでした。この事例の最も大きな失敗は、午後2時に利用者を見失った後、職員だけで3時間も探してしまったことです。大きな施設であれば、必ず管理事務所がありますから、捜索の協力をしてもらったり、施設の放送設備で呼び出してもらって来場者に協力を求めることができます。3時間も経ってからではもう施設内を出てしまっていたでしょうから、捜索協力を求めても無意味です。見失った直後に職員の一人が管理事務所に応援を求めに行けば、施設内で発見することができたかもしれません。
このように、利用者を見失うというミスを想定して、「管理事務所に職員が応援を求めに行く」というルールにしていなければならないのです。当然、管理事務所があって迷子(※)の呼び出しができるような施設をあらかじめ選んでおかなくてはなりません。■外出行事中だけ利用者に目印を付けてはいけないか?
私たちは、幼児を連れて遊園地に行って子供を見失ってしまったら、管理事務所に行って迷子の呼び出しをしてもらいます。この時、子供が誰から見ても判別できる特徴がある服を着ていると、発見が早くなります。逆に言えば、幼児を連れて人混みに出かけるのであれば、「特徴がある服を着ているといざと言う時見つかりやすい」ということになります。かつて私の家でも子供とディズニーランドに行く時は、特徴のある服をわざわざ着せていましたから、「スターウォーズと書いた赤のTシャツを着た男の子が…」と呼び出してもらうとすぐに見つかったことがあります。
同様にグループホームの外出行事でも、利用者に特徴のある服を着てもらえば、施設内放送で呼び出しを行った時に見つかりやすくなります。高齢者のパッケージツァーなどでは、コンダクターが旗を振って旅行者がみな同じワッペンを胸に付けています。ツァーの参加者ははぐれたら困りますから、少し恥ずかしくても素直に目印を胸に付けているのです。
グループホームの外出行事の時に、まさか「○○グループホーム」というワッペンを胸に付ける訳には行きませんから、本人が抵抗なく付けられ、また尊厳を損なわないような工夫をしてあげれば良いと思います。あるグループホームで行事参加者に、「式典の来賓の胸に付ける胸章リボン」を付けたところ、「何の行事ですか」と周囲から尋ねられたという話がありますが、人を探すとき目印になるものであれば何でも良いのです。
施設の職員は行事先の下見などをして、不都合が起こらないかどうか下調べを熱心に行いますが、不都合が起きた時の対応も想定してルール化して欲しいのです。
※大人の場合、正式には「迷子」ではなく「迷い人」と呼びます。